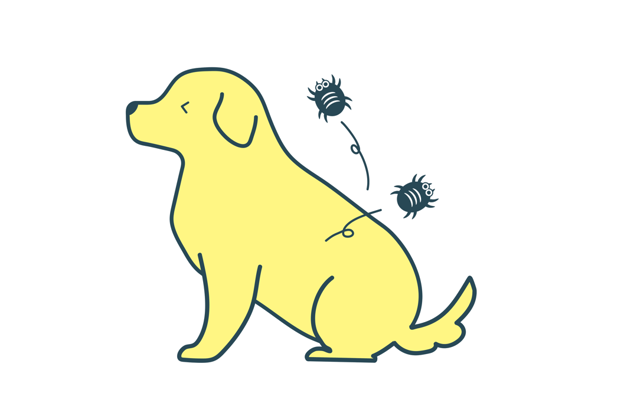ペットにおいてワクチン接種は非常に重要です。世界小動物協会(WSAVA)は、犬と猫のワクチン接種に関するガイドラインの作成を行なっています。
2007年、2010年、2016年にガイドラインを発行しており、今年2024年に最新版のガイドラインが発表されました(現時点で日本語版はまだなし)。ワクチネーションガイドライングループ(VGG)は、コアワクチンとノンコアワクチンについての定義づけを行いましたが、今回のガイドラインでもより定義を強固なものにしています。
注目すべき点をご紹介するとともに、今回のガイドラインでは質問コーナーが充実しており、全てをご紹介することは誌面の都合上難しいのですが興味深いところをいくつかお示しします。
目次
2024年版コアワクチン・ノンコアワクチンの定義
◆コアワクチン:
コアワクチンは重要な感染症に対して、防御のため、全ての地域の犬・猫への接種が推奨されるワクチンです。犬では、犬ジステンパー(CDV)、犬アデノウイルス(CAV-2)、犬パルボウイルス(CPV-2)がコアワクチンで、猫では猫汎白血球減少症(FPV)、猫伝染性鼻気管炎ウイルス(FHV-1)、猫カリシウイルス(FCV)がコアワクチンに含まれています。
◆今回アップデートされた点:
狂犬病が発生している国においては狂犬病や、レプトスピラの流行地域では、それも犬のコアワクチンの一つになりました。また、猫の猫白血病ウイルス感染症 (FeLV)ワクチンも、感染が流行している地域に住む1歳未満の若い猫や、流行地域で屋外に出る機会のあるような暴露リスクの高い成猫ではコアワクチンと定義されています。
ノンコアワクチンは地理的、ライフスタイル(室内・屋内飼、多頭飼いなど)の違いによりリスクが高まる場合に定義されます。
ワクチン接種スケジュール
子犬と子猫のコアワクチンの 初年度接種の最後を16週齢またはそれ以降とし、ブースター接種は26週齢 またはそれ以降での追加接種と記載しています。これは、母親由来の抗体(MDA)が存在する個体をもれなく免疫化するために実施します。
狂犬病ワクチン
狂犬病が風土病的に見られる地域(endemic)において、法的に義務付けられていなくても猫に予防接種をすることを推奨しています。
レプトスピラワクチン
初回接種は生後8週から、2回目は2~4週間間隔で実施し、それ以降は毎年の接種を推奨しています。血清群は地域によって異なるので、その地域で流行している血清に対する製品を選ぶ必要があります。
シェルターにおけるワクチン接種
シェルターでの集団の健康を維持するため、コアワクチン接種に関して下記3点推奨しています。
- 入所時に全ての個体にコアワクチンを接種すること。
- 迅速に保護効果を発揮するワクチンを使用すること。
- 幼若動物においては1ヶ月齢から初回のワクチネーションを開始し、シェルターにいる期間は5ヶ月齢に至るまで2~3週ごとにワクチンを繰り返し接種すること。
興味深い質問
今回のガイドラインでは、質問コーナーが解説されていました。著者が興味を惹かれたものをいくつかご紹介しますが、ここに載せたもの以外にも多数の質問がありますので、ご興味があればぜひチェックしてみてください。
Q:犬コロナウイルス(CCoV)ワクチンはなぜ推奨されないという扱いなのですか?
A:子犬の犬コロナウイルス(CCoV)感染は、生後早期に発生し、ワクチンプロトコルが開始する前に起きることもあります。また、ワクチン接種された犬では、腸内のIgA抗体による反応の発達が不十分になることも示唆されています。感染による下痢は通常軽度で、変異株は成犬や子犬において、重度の嘔吐や全身性疾患を引き起こすことが時折報告されていますが、現在入手できるCCoVワクチンが変異株に対して有効であるという根拠は乏しいことなどから、推奨されていません。また、犬用のコロナウイルスワクチンを接種しても、新型コロナウイルス感染症(COVID19)に対する防御効果はありません。
Q:子犬や子猫が初乳を摂取しなかったとき、母親からの移行抗体による感染防御は期待できますか?
A:母親の移行抗体価にもよりますが、保護効果はあまり期待できないか、全く期待できない可能性が高いです。移行抗体の95%以上は初乳から得られ、これは生後24時間まで、特に最初の4時間に腸管を通じて吸収されます。
Q:高齢犬のワクチン接種の停止を考慮すべき年齢は?
A:高齢であっても、特にコアワクチン接種は3年以上の間隔で再接種することが必要です。レプトスピラワクチンなど、ノンコアワクチンは通常毎年の接種が重要になります。
Q:小型、または超小型(tiny)犬に対して、ワクチン接種による副反応(adverse reaction)リスクを低減させるため、規定量の半量や1/4量を投与することはできますか?
A:これは推奨されません。小型犬ではワクチン接種による副反応の発現が多くなるというエビデンスがあるとともに、抗体価は大型犬や超大型犬より高くなり傾向にあります。しかし、重篤な副反応は稀であり、副反応は体格よりも犬種に関連する可能性があると示されています。また、一部のワクチンは副反応に関連するウシ血清アルブミンの濃度を大幅に減少させる取り組みを行なっています。また、小型犬用により小さい容量(0.5mL)に調整した製品も開発されています。

Q:猫において、”過剰ワクチン接種”が慢性腎臓病(CKD)を引き起こすことがあるというのは本当ですか?
A:FPV、 FCV、FHVを含む一部のワクチンには、Crandell-Rees猫腎細胞を用いて精製されています。実験ではCRFK細胞ライセートやCRFK細胞で培養されたワクチンを摂取すると、CRFK細胞に結合する抗体が産生されます。CRFK細胞ライセートを用いた実験的過剰接種(最初の50週間に12回、その後1年後にもう一度)では、6匹の猫のうち3匹にリンパ形質細胞性間質性腎炎が発生しました。しかし、FPV、 FCV、FHVワクチンを使用した最近の過剰接種研究(14週間に8回の接種)では、過剰接種がCKDや間質性腎炎を引き起こすことはなく、成猫における頻回の接種がCKDを引き起こすかはまだ証明されていませんが、ワクチンの不必要な過剰接種は避けることが重要です。
まとめ
今回のガイドラインでは、従来から定義されていたコアワクチンの適応病原体に加え、いくつか細かい変更・追加が入りました。流行地域でのレプトスピラや狂犬病のワクチン接種の重要性が強調されたほか、臨床家から受けることが多いであろう質問集も添付されていました。
狂犬病予防接種に関しては、日本は清浄国なのでガイドラインとしてはコアワクチンとはなりませんが、狂犬病予防法により法的に接種が義務付けられています。日本では長らく発生していないので、飼い主さんから摂取について疑問を受けた経験もあるかもしれません。海外の多くの国で散発的にではありますが、毎年発生していること、海に囲まれた地理的条件が同じ台湾でも2013年に狂犬病が発生し、イタチアナグマから犬に感染し、犬が死亡したことがありました。日本にもいつどのようなルートで狂犬病が入ってくるかわかりません。何より人間の身を守るためにも接種の重要性をアナウンスしていく必要があります。
他にも、混合ワクチン接種時に飼い主さんから「いつまで打つのか?」「レプトスピラは毎年打たなければいけないのか?」など聞かれる場面も多いかと思います。飼い主さんとのコミュニケーションにもお役立ていただければ幸いです。
参考
・R. A. SquiReS *,1, C. CRAwfoRd†, M. MARCondeS‡ And n. whitley, 2024 guidelines for the vaccination of dogs and cats – compiled by the Vaccination Guidelines Group (VGG) of the World Small Animal Veterinary Association (WSAVA), https://wsava.org/wp-content/uploads/2024/04/WSAVA-Vaccination-guidelines-2024.pdf
監修者プロフィール

獣医師
福地可奈
2014年酪農学園大学獣医学部卒業したのち、東京都の動物病院にて4年間勤務し犬や猫を中心とした診療業務に従事しました。
2024年3月末、東邦大学大学院医学部博士課程の単位取得。春からは製薬企業に勤務しつつ、学位取得要件である博士論文の提出を目指して活動しております。
獣医師や一般の飼い主様に向けた動物の中毒情報を発信するなど、臨床とは異なったアプローチで獣医療に貢献することを目標に活動しています。
犬猫の中毒予防情報webサイト(外部webサイトに遷移します)