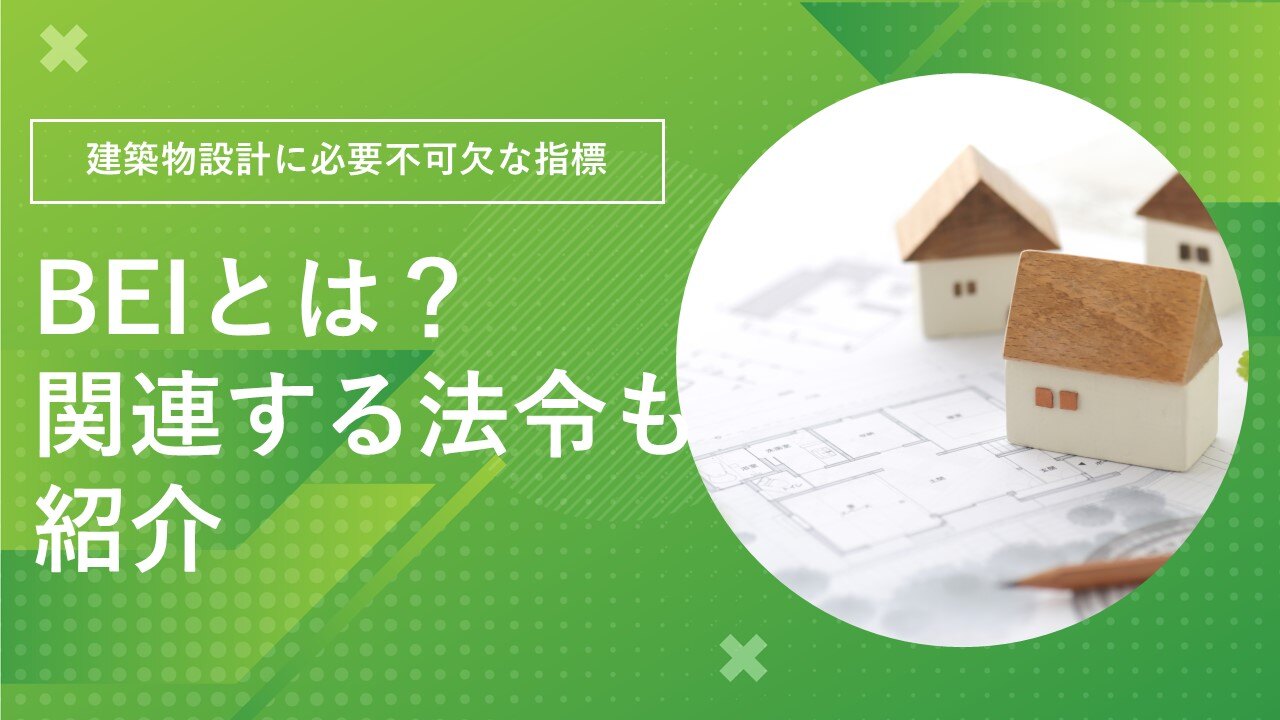建築物の省エネ性能が注目される中、設計士にとって重要な指標となるのがBEIです。
2025年4月以降、原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が義務化されることから、BEIの理解は設計において不可欠な要素となっています。
この記事では、BEIの基本的な概念から関連する制度、そして実際の設計に活かせるBEI値の改善方法まで、詳しく解説していきます。
\機器選定から設計書類作成まで"無料"サポート/
目次
■この記事でわかること
- BEIの基本的な概念と計算方法
- BEIに関連する主な制度と基準値
- BEI値を下げるための具体的な方法
BEI(Building Energy Index)とは
BEIとは、建築物省エネ法において、建築物の省エネ性能を示す重要な指標です。国が定めるBEIの基準を1としたとき、その建築物のエネルギー消費量がどれくらいであるかを数値で示します。
たとえば、当該建築物のBEIが0.80であれば、その建築物の消費エネルギーの削減率は20%ということになり、0.70であれば30%の削減率となります。つまり、BEIの値が低くなるほど、建築物の省エネ性能が高いことを示しています。
BEIは以下の計算式で求められます。
BEI = 設計一次エネルギー消費量 ÷ 基準一次エネルギー消費量
■設計一次エネルギー消費量とは:
≫当該建築物の設計仕様を基に算定した一次エネルギー消費量
■基準一次エネルギー消費量とは:
≫設備・地域・用途ごとに定められた基準となる標準的な一次エネルギー消費量
■一次エネルギー消費量とは:
≫「空調・換気・照明・給湯・昇降機(非住宅のみ)・その他(OA機器等)」のエネルギー消費量から、再エネ設備(太陽光発電システム等)によって生み出されるエネルギーを減じた値
_02.webp?width=600&height=175&name=bei(%E3%81%A8%E3%81%AF)_02.webp)
引用:エネルギー消費性能 | ラベル項目の解説|建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表⽰制度|国土交通省
このような計算方法により、建築物の省エネ性能を客観的に評価することが可能となり、設計段階での省エネ性能の確認や改善に活用できます。
BEIを用いる主な制度
- 省エネ基準適合義務制度
- 住宅トップランナー制度
- BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)
省エネ基準適合義務制度
建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度により、住宅と非住宅ごとに「省エネ基準」としてBEIの基準が設けられています。
|
建築物の種類・用途 |
一次エネルギー消費量基準(BEI) |
|
|
住宅 |
1 |
|
|
非住宅(※) |
工場等 |
0.75 |
|
事務所等・学校等・ホテル等・百貨店等 |
0.80 |
|
|
病院等・飲食店等・集会所等 |
0.85 |
|
2025年4月以降は、原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合義務が課されるため、BEI値が基準を満たすよう設計しなければなりません。基準を満たさない場合、省エネ適判NGとなり確認申請が不可となります。
住宅トップランナー制度
住宅トップランナー制度とは、規格化された住宅を一定以上提供する大手住宅事業者に対し、より高い省エネ基準への適合を努力義務として課す制度です。以下のとおり、住宅の種類と年間あたりの供給戸数、目標年度ごとに省エネ基準としてBEIの基準が定められています。
|
住宅の種類 |
年間あたりの供給戸数 |
一次エネルギー消費量基準(BEI) |
目標年度 |
|
建売戸建住宅 |
150戸 |
0.85 |
2020年度 |
|
注文戸建住宅 |
300戸 |
0.80 |
2024年度 |
|
賃貸アパート |
1,000戸 |
0.90 |
2024年度 |
|
分譲マンション |
1,000戸 |
0.80 |
2026年度 |
目標年度とは、省エネ基準をいつまでに達成するかを示したものです。なお、それ以降も継続して達成し続けることが求められます。
また、トップランナー制度における省エネ基準には見直し案が出ており、2027年度にはより高い水準となるかもしれません。例えば、建売戸建住宅のBEIの基準は現行では0.85ですが、2027年度には再エネ設備を除いて0.80へと見直す案が出ています。
BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)
BELSとは、建築物を販売・賃貸する事業者に対して、建築物の省エネ性能を表示することを義務として課す制度です。建築物を購入・賃貸する人が省エネ性能への理解を深め、省エネ性能で建築物を選べるようにすることを目的としています。
評価機関で省エネ性能が評価され、その結果がラベルや評価書に記載されます。BEIは星で評価され、星の数が多いほど省エネ性能に優れた建築物であることを証明しています。
引用:建築物省エネ法に基づく省エネ性能表示制度事業者向け概要資料|国土交通省
星の数は以下のとおり、一次エネルギー消費量の削減量(BEI)に応じて決定されます。_04.webp?width=600&height=338&name=bei(%E3%81%A8%E3%81%AF)_04.webp)
住宅の場合、星の数が1つで省エネ基準を達成、星3つで誘導水準(ZEH水準)を達成します。非住宅の場合は、建築物の用途に応じて星の数が2~3つで省エネ基準を達成、建築物の用途に応じて星が4~5つ以上でZEB水準を達成します。
■誘導水準(ZEH水準)とは:
「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)=エネルギー収支ゼロをめざした住宅」の認定基準
■ZEB水準とは:
「ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)=エネルギー収支ゼロをめざした非住宅」の認定基準
BEI値を下げる方法
BEI値の低減は、これからの建築設計において避けて通れない重要な課題です。省エネ基準適合義務制度や住宅トップランナー制度、BELSなど、各制度で定められた基準を満たすためには、建築物の省エネ性能を効果的に向上させる必要があります。
BEI値を構成する一次エネルギー消費量は、空調・換気・照明・給湯・昇降機(非住宅のみ)・その他(OA機器等)のエネルギー消費量から、太陽光発電システムなどの再エネ設備による創エネルギー量を差し引いて算出されます。したがって、BEI値を下げるためには、これらの要素に着目した対策が効果的です。
具体的には、高効率設備の採用による消費エネルギーの削減、住宅性能の向上による熱負荷の低減、そして再生可能エネルギーの導入による創エネルギーの確保が重要な方策となります。以下では、これらの対策について詳しく解説していきます。
高効率設備の採用
BEI値の改善において特に即効性の高いアプローチが、高効率設備の採用です。とりわけ、建物全体のエネルギー消費量の大きな割合を占める設備を高効率機器に置き換えれば、大幅な省エネ効果が期待できます。
以下のグラフが示すように、空調・換気設備と照明は、建物全体のエネルギー消費量の中で大きな割合を占めています。これらの設備の効率を向上させることで、BEI値の低減につながります。
空調設備では、高いエネルギー効率を実現する最新型のエアコンを選択することが重要となります。
換気設備では、全熱交換器の導入が効果的です。全熱交換器は、室内の空気を排出する際に含まれる熱エネルギーを回収し、取り入れる外気に戻すことができる設備です。これにより、換気に伴う熱ロスを最小限に抑え、空調負荷を大幅に低減できます。
照明設備においては、LED照明の採用が省エネ性能の向上に大きく貢献します。従来の蛍光灯と比較して消費電力が少なく、長寿命である特徴を活かすことで、エネルギー消費量の削減とメンテナンスコストの低減を同時に実現することが可能です。
パナソニックでは、これらの設備設計に関する無料サポートを提供しています。エネルギー消費量の削減と快適な環境づくりのための、最適な空調・換気システム、照明をご提案。
専門スタッフが作成した設備プランは、設備設計会社への依頼にもそのまま流用できるため、多くのお客様から好評をいただいています。
\設備設計に関する手間を"無料"で削減/
住宅性能の向上
建築物の基本性能を高めることは、長期的な省エネ効果を得るための重要な方策です。特に、断熱性と気密性の向上は、空調負荷の低減に直接的に寄与します。
高性能な断熱材やLow-E複層ガラスなどを採用すれば、室内外の熱の出入りを効果的に制御できます。これにより、室内の温度変化を抑えられ、冷暖房の使用頻度や負荷を大幅に抑制することが可能です。
また、建物の気密性を向上させることで、隙間風による熱損失を防ぎ、より効率的な空調環境を実現できます。
これらの対策は、居住者の快適性向上にも直結する重要な要素となります。
再生可能エネルギーの導入
再生可能エネルギーの活用も、BEI値の改善における効果的な方策です。太陽光発電システムなどの再生可能エネルギー設備で生成されるエネルギーは、一次エネルギー消費量から差し引くことができるため、BEI値の大幅な改善につながります。
この取り組みが重視される背景には、国が推進する「地球温暖化防止」と「エネルギーの安定供給確保」という二つの重要な政策目標があります。再生可能エネルギーは、化石燃料と異なり温室効果ガスを排出しないため、地球温暖化対策として非常に有効です。
さらに、エネルギー資源の多くを海外に依存している日本において、再生可能エネルギーの導入拡大は、エネルギー自給率の向上と供給の安定化に貢献します。建築物の所有者や使用者にとっても、光熱費の削減という経済的なメリットをもたらすため、再生可能エネルギーの導入は多面的な価値を生み出します。
まとめ
BEIは建築物の省エネ性能を客観的に評価する重要な指標です。2025年4月からの省エネ基準適合義務化に向けて、その理解と対応が不可欠となっています。建物の用途や規模によって求められる基準値は異なりますが、いずれの場合もBEI値が基準を満たさなければ確認申請が不可となります。
省エネ性能の向上には、建物全体のエネルギー消費量を構成する各要素への適切な対策が重要です。特に、空調・換気・照明設備は消費エネルギーの大きな割合を占めるため、これらを高効率機器に更新することで大きな省エネ効果が期待できます。
たとえば、全熱交換器の導入は換気時の熱損失を最小限に抑え、空調負荷を大幅に低減できます。この設備は室内の空気を排出する際の熱を回収し、取り入れる外気に移行させることで、効率的な換気を実現します。
しかし、全熱交換器をはじめとする設備の設計には、建物に合わせたシステムの選定や、効果的な運用に向けた綿密な計画が求められるため、専門的な知識が欠かせません。
パナソニックでは、空調・換気・照明設備の設計に関する無料サポートを提供しています。経験豊富な専門スタッフが、省エネ性能の向上と快適な室内環境の両立に向けて、最適な設備プランをご提案いたします。機器選定から設計書類の作成まで一貫してサポートすることで、設計者の皆様が本来の設計業務に注力できる環境を整えていますので、ぜひご相談ください。
\機器選定から設計書類作成まで無料サポート/
Author 執筆者情報

横松建築設計事務所
代表取締役 / 一級建築士 横松 邦明 氏
国内外で100棟以上の建物の計画/設計経験あり。企業/建築士会/建築士事務所協会等の講演も行っている。
BIMを黎明期以前より取り入れ研究してきた背景から、国土交通省へ協力する日本建築士会連合会BIMタスクフォースのメンバーとして、国内有数のメンバーと共に様々な活動を実施中。現在は東京、栃木、新潟のオフィスを拠点に設計活動を行っている。